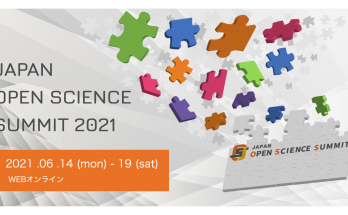| 日 時 | 2018年9月27日(木) 19:00-20:30 |
| スピーカー | 三ツ村崇志さん(株式会社ニュートンプレス) |
| 場 所 | MTRL KYOTO |
当日のメモは以下からご覧ください。
メモ
メモ 当日参加者13名(世話人3名+スピーカー1名含む)
『Newton』とは?(広報資料参照)
- 1981年創刊の科学雑誌
- 約11万部発行
- 約8割の読者が男性(10代、40~50代)
- 月刊誌、別冊、ライト、iPad版
- 根強い固定ファン
制作の流れ
- イラスト案の作成
- 文章を読まなくても何のイラストか理解できるか?
- 科学的な間違いはないか?
- 印象的で美しいか?
- 文章の校閲、事実確認
- 事前情報なしでも内容や雰囲気を理解できるか?
- 科学的な正確性を損なっていないか?
- 論理に飛躍はないか?
- 素直に面白いか?
編集者の仕事とは?
- 企画をつくることが最大の仕事
- どのような分野でも担当する
- 読者の目線を想像する。読者が持ちやすい疑問や,読者の文脈で「すごい!」と思える面白い内容を考える。
- これは研究者文脈での面白さとはまた違うもの
ネット時代の科学雑誌とは?
- ライバルはスマホ?。「消費者の時間をいかに奪うか」が鍵
- 他社の科学雑誌は書誌コーナーを維持するための「同志」
- 月刊誌に速報性を求めるのは不利。時事ネタをやるなら記事の「深み」を追求。
- 固定ファンを離さない
- すでに社会的に科学雑誌としての認知されているので,「何か(科学に関して)面白いものないかな」と思った時に手にとってもらえるような信頼性ある記事を出し続けることが重要では?
科学の研究成果をうまく伝えるためには?
- プレスリリースでは対象を意識して,読者をひきつけるタイトルが重要
- (研究者ではなく)一般の人の文脈での「面白さ」が伝わる工夫
- 読者の疑問や状況を想像する力、共感力
オープンサイエンスについて(私見)
- シチズンサイエンス
- 科学雑誌の編集者としては,手法よりもそこから出てくる研究結果が面白いかどうかにまず興味を持っている
- 「市民参加」という形式自体への興味は,新聞など一般メディアの方があるかもしれない
- 参加者を増やすには?
- 「すぐできる」「何だか楽しい」という要素が必要か?
- インセンティブの設定が重要では?
- 「参加しなければならない」,「参加したい」と思わせる,「言い訳」 が用意されているプロジェクトは成功しやすいのかもしれない。
- ある程度の規模になると「みんなやっている」という空気感が出るので,参加が加速するのでは?
情報の広げ方について最近起きていること
- Twitter、SNSなどのコミュニティベースのコミュニケーション
- 相手を想像しやすい
- 「より多くの人へ」から「(このテーマを)好きな人へ」
- コミュニティの「外」の人に伝えるには?
- 異分野のコラボレーションによってコミュニティ境界を拡張する
- 例:科学とアートのコラボによって、アートに根ざしたひとに科学を伝える(逆もあり)
- 昔から使われている手法だが効果的
- ただし、親和性の高いコミュニティの間しか使えない
- 科学を嫌いな人に科学の面白さを伝えるには?
Q&A
- Q. 企画を考えるときに心がけていることは?
- A. 読者目線に立ち想像する。色々な場所に出かけて情報を収集する。読者の目線を想像するために、自分の専門以外の分野に積極的に触れるようにしている。
- Q. タイトルはどうつけると良いか?
- A. 情報を届けたい相手を想像して,適した文言を考える。読者が一般の方のときと,専門家のときでは,タイトルをつけるときに考えることは変わるはず。
- Q. 論文はどうやって手に入れる?
- A. 必要な場合は購入している。
- Q. 読者にどういったことを望む?
- A. ネットだと欲しい情報を検索して調べることが多いので,「なにか面白いものを探したい」という少し漠然なときに,月刊誌を見てもらえるようになると嬉しい。月刊誌で興味をもったテーマがあれば,別冊などのまとまっているものを見てもらいたい。
- Q. 読者層が男性に多いのはなぜ?
- A. 詳しい理由は分からないが、読者にエンジニアや研究者が多いことも関係してるのかも?
- Q. 編集部で新しい動きはある?
- A. 社の見解は分からない
- Q. 最近のNewtonは昔のNewtonと変わってきた?
- A.基本的なスタンスが変わってきたということはないのでは? もちろん,その時々の編集部の人員や流行りなどで内容の傾向が変わることはあるとは思うが・・・